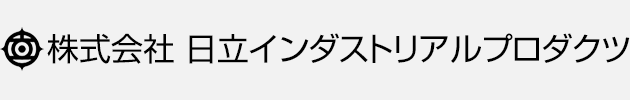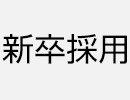モノづくりの最終段階で、 品質と信頼性を守り抜く。 モノづくりの最終段階で、 品質と信頼性を守り抜く。
- 鮎川 秀平
- Shuhei Ayukawa
電機システム事業部 ドライブシステム本部
電機品質保証部 / 2017年入社
工学部 機械知能工学科 卒
入社の決め手
私が就職活動をしていたのは、当社が日立製作所から分社する前でした。参加したインターンシップで目にしたのは、技術をより生かすにはどうしていくべきか、お客さまと密に連携をとりつつ社会イノベーションを進めようとする姿でした。高い技術力を一方的に売るだけではない点に感動し、入社を志望しました。
いまの仕事について
品質を守り、 製品の信頼性を保証する。 品質を守り、 製品の信頼性を保証する。
製品の性能に誤りがないことを確認し、正しく評価する「品質保証業務」を担当しています。いわばモノづくりの最終段階で、当社製品の信頼性を保証する役割です。性能が、定められた仕様にわずかでも満たなければ、お客さまに引き渡すことはできません。自社の製品であっても客観的なジャッジが求められます。
当社で作っている製品はさまざまですが、私は、非常時などに電力を供給する自家発電設備を担当しています。自家発電設備は、当社製の発電機のほか、原動機、制御盤、補機類など、多くの機器の集合体です。他社からの購入品も含め、まずは一つずつ機器を検査した後、工場内での機器を組み合わせての確認を行い、問題がなければ現地へと出荷します。さらに現地での試運転検査を行い、最終の性能確認をします。最後に、発電設備の操作方法や異常時の対応などをお客さまにレクチャーし、ようやく引き渡しとなります。
製品の納入後に何か問題が起きれば、お客さまの業務、ひいては多くの方々に影響を及ぼすことになります。だからこそ、ダブルチェックや指差呼称といった基本を徹底し、あらゆる懸念がなくなるまで愚直に検査しきるよう心がけています。また、万一不具合が見つかった場合は、「この問題は、他の製品でも起こりうるのでは?」と考え、社内できちんと共有、改善を図る。そうした対応も、品質に妥協しない日立の品質保証の大切な仕事だと考えています。


いまの仕事について
幅広い製品・公共性の高い施設に、 この手で関わることができる。 幅広い製品・公共性の 高い施設に、 この手で 関わることができる。
当社の製品に限らず、他社の製品などさまざまな製品に触れ、現地で動く様子を見ることができるのは面白いと感じます。実際に仕組みを目で確かめてみなければ得ることのできない知識が多くあります。
また、大規模なビルや水道局などの公共性の高い施設に製品を納めることができるのも醍醐味です。日立グループの一員として、社会の根幹を支えるモノづくりに関わることができるのは、まさに当社ならではの魅力といえます。自家発電設備は、東日本大震災以降、非常時の備えとして、確実に動くものが強く求められています。その分私たちが行う検査には、大きな責任が伴います。設置する場所や機器の組み合わせ、工事スケジュールの制約など、毎回条件が異なるため、実施する検査も同じというわけにはいきません。水道局の場合、既存の古い設備を一部だけ更新するケースもあり、基盤となるシステムが日立製ではないこともあります。社内・社外問わずさまざまな分野の方と入念なやりとりをし、最善の検査計画を立て、一つ一つの過程を無事に乗り越える。そうしてお客さまに製品を引き渡した際には、やはり大きなやりがいを感じます。


仕事を通じて成長したこと
日々の業務を、 知識と技術を磨く機会に変え続ける。 日々の業務を、 知識と技術を 磨く機会に変え続ける。
ターニングポイントとなったのは、「コンバインドサイクルシステム」と呼ばれる発電設備の検査を経験したことです。システムの構造は、ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせた、とても複雑なものです。検査では、社内試験をはじめ、施工時における試験、法規に基づく自主検査と、3段階の試験を実施し、その結果、試運転の期間は約1年にも及びました。さらに、万が一の故障発生時にシステムの保護回路が正しく動作するかの確認試験も300通り以上行ったため、正直、システムや書類作成の複雑さや、現地でのやりとりの多さにへきえきとしてしまうこともありました。そんなときに、一緒に試運転を担当した方から掛けられたのが、「興味を持ってやったら仕事も覚えるし、何より楽しいよ」という言葉。仕事への向き合い方を新たにしたことで、長期に及んだ試運転を無事故無災害でやりきることができました。
また、ちょうど同じ時期に私は、電気設備に関する活躍の幅を広げるために、国家資格である第二種電気主任技術者の資格取得にも挑戦しました。膨大な数の検査に向き合う中でも、「座学で学んだことと、今関わっているシステムが一致する部分もある」と理解が深まる瞬間が多くあり、資格の取得につなげることができました。当社にはもともと充実した教育環境がありますが、学びの機会はそれだけではありません。今後も、一つ一つの仕事を、知識と技術を磨く機会に変え続けていきたいです。


日立インダストリアルプロダクツの魅力
日立の創業製品と、 培われたノウハウを受け継ぐ。 日立の創業製品と、 培われたノウハウを受け継ぐ。
日立インダストリアルプロダクツは、日立の創業製品である電動機の製造を受け継ぐ会社です。日立が電動機を製造してから100年以上という歴史は、まさに日本における電動機の歴史そのものです。当社のモノづくりに、そうした歴史が大きく反映されていることが、製造の基準などを見るとわかります。過去の資料を調べてみると、「いつ書かれたんだろう」といった、かなり古めかしい記録まで残っていることがあります。多くの技術者たちが研さんを積み重ねながら、成功や失敗を繰り返して、モノづくりの精度や品質が高められてきたのだと感じます。お客さまが期待しているのも、そうした日立ならではの信頼性や品質だと感じます。
今後は、品質保証業務の効率化や技術伝承に向けて、業務のデジタル化を進めていきたいと考えています。例えば、製品の規格や仕様書などをデータ化することで、製品の問題に対する解決策を生成AIが提示するということが可能になるかもしれません。実現にあたっては、AI技術の正確性も、品質保証としてしっかり担保する必要が出てくるでしょう。新しい技術を適切に活用しながら、長年受け継がれた信頼性と品質を、この先につないでいけたらと思います。