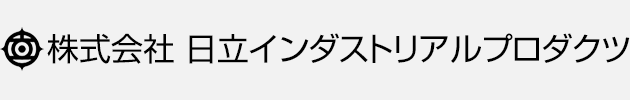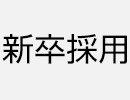仕入れの力で、 日本のモノづくりと、 社会の当たり前を支える。 仕入れの力で、 日本のモノづくりと、 社会の当たり前を支える。
- 荒川 拓巳
- Takumi Arakawa
調達本部 電機システム調達部
ドライブシステム調達グループ / 2021年入社
文学部 国際文化学科 卒
入社の決め手
就職活動で日立グループの合同会社説明会に参加した際に、新幹線用のモータを製造している当社が印象に残りました。企業研究を進めると、日立製作所発祥の工場を受け継ぐ会社であり、数ある日立グループの企業の中でも日立の本流であると感じました。また、栃木県出身の私にとって、同じ北関東の茨城県発祥である日立の風土は肌に合うのではと考え、入社を決めました。
いまの仕事について
世界のマーケットを見つめ、 最適な部品を仕入れる。 世界のマーケットを見つめ、 最適な部品を仕入れる。
私は、現在「調達」という仕事でバイヤーをしています。調達とは、製品をつくる際に必要となるさまざまな部品や機器を仕入れること。例えば、ひと口に「モータをつくる」と言っても、そのモータは、空気冷却機やブレーキ、油圧装置などの大型機器から、モータ内部に組み込まれるカーボンブラシや温度計、バルブなどの小型部品まで、多くの他社製品によって構成されています。そうした構成部品を、設計上の仕様を満たしながら、いかに最適な品質の物を適正な価格で購入し、適切なタイミングで工場に揃えるか。それがこの仕事のミッションです。
設計部から受け取る仕様書には、部品の仕様は書かれていますが、どの調達先の部品を仕入れるかは、私たちバイヤーに委ねられます。その時々の市況や世界情勢を考慮しながら、日本国内だけでなく海外の調達先とも価格交渉を行い、最もふさわしい取引先を選定します。そして発注後は、期日通りに納品されるように納期を管理することも大事な役割です。ネットショッピングのように購入ボタンを押せば希望日に商品が届くわけではなく、特に海外との取引では、納期通りに進まないことも少なくありません。地域によっては紛争などの影響を受けることもあり、取引相手の商習慣やワークスタイル、価値観も異なります。そのような状況の中でも、品質や納期を妥協することなくベストな部品を用意することが、調達の役割だと考えています。


いまの仕事について
丁寧な対話と交渉の力で、 利益を生み出す。 丁寧な対話と 交渉の力で、 利益を生み出す。
調達の仕事は、価格と納期の交渉が中心です。現在は私一人で年間10億円規模の仕入れを担当していますが、買値を下げることができれば、その分が会社の利益に直結します。自分の思い描いた通りに交渉を進め、会社に利益を生み出すことができたときには、この仕事の面白さを感じます。
一方で、自分たちだけが良い思いをするのではなく、お客さまや調達先の潜在的な思いに耳を傾けながら、三者にとって良い取引を模索することも大切だと考えています。
ターニングポイントになったのは、ダンプトラック向けのモータに使用する部品の取引でした。ある時、調達先の会社から、その部品を値上げしたいという連絡がありました。しかしその部品は、お客さまからは価格を下げるように強く要望されていた部品でもありました。
私は、関西にある調達先の会社まで足を運び、値上げの背景や製造状況をお聞きしました。すると、人件費や材料費の上昇のほかに、性能には関係のない美観のための研磨をしていただいていることが分かりました。それは、過去の当社との取引の中でいつの間にか追加されていた“サービス”で、調達先にとっては負担になっている工程だったのです。その工程をなくせば値下げできることが分かり、私は美観部分の仕上げ仕様の緩和を提案し、お客さまにも承認を得ることができました。
私たちが調達先を訪問する際には、どうしても価格や納期の相談が多くなりがちです。しかし、困りごとがないと動かないという姿勢ではなく、できるだけ多くの調達先を訪問し、日頃から丁寧なコミュニケーションを図っていきたいと考えています。


仕事を通じて成長したこと
ただ手配するだけではない、 課題解決型のバイヤーへ。 ただ手配するだけではない、 課題解決型のバイヤーへ。
調達の仕事は、仕様書に従ってただ部品を手配するだけでは、価値を発揮することはできません。入社したばかりのころは、設計部や製造部、調達先の営業の方など、部品やモノづくりのエキスパートに囲まれて、情報のやりとりに食らいつくだけで精一杯でした。
しかし、少しずつその中で飛び交う情報の意味や、調達だから予見できる懸念点が見えてくるようになりました。例えば、調達先の納期がひっ迫しそうであれば、社内での手配を早めてもらうように働きかけたり、紛争や世界情勢を鑑みて、輸送時に起こりうる懸念点を事前に周知したり、また、法律や契約上の注意点を工場側に伝えたりすることもあります。
調達が間に入るからこそ生み出せる価値は何か、他部署からどんなことが求められているのか、この数年を通して、より高い視座から考えることができるようになってきたと感じます。
それでも調達の仕事は奥が深く、知識だけでは解決できないことがあることも痛感しています。今後は、広く知識を吸収するだけではなく、それらをどう使うか、使い方やタイミングを身につける必要があります。そのためには、さまざまな課題を乗り越えながら経験を積み重ねるしかないと思います。現状に満足することなく、自分の知識と経験を深め、課題解決型の調達バイヤーになりたいと思っています。


日立インダストリアルプロダクツの魅力
この国のモノづくりと、 人々の生活を支えることができる。 この国のモノづくりと、 人々の生活を 支えることができる。
日本のメーカーが次々と海外に製造拠点を移していく中で、当社では設計・製造・品質保証のプロセスを同じ工場内で行い、事務所の隣で製造を行っています。私は日頃から、海外を含め多くの他社製品に触れていますが、当社の製品の品質は日本屈指のものであると確信しています。設計思想や品質基準を通して見ると、日立製作所発祥の工場として、「モートルの日立」と言われるだけの実力と品質がここにはあります。日立の源流として100年以上続いてきた技術力、品質を間近で体験しながら仕事ができる。そして、日本屈指の技術力を持って世界を相手に戦うことができる。それは、当社で働く大きな魅力だと思います。
また、当社は2023年に「モノづくりの力で、ステキな未来をつくる」というパーパスを策定しました。私はこれを「当たり前のことを当たり前にできる生活を、次の世代につないでいく」ということだと解釈しています。当社の製品は、見えないところで社会のインフラや人々の生活を支えているものが多いです。電車に乗って遠くまで行ける、蛇口をひねれば水が出る、普段は気にも留めないそんな「当たり前」ですが、意識することがないのは、大きな故障や事故がなく稼働し続けている証拠でもあります。品質の高い日本のモノづくりを通して、私たちが当たり前に享受している生活を次の世代の子どもたちに受け継いでいくことが、当社の担う社会的な役割だと考えています。